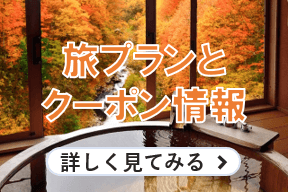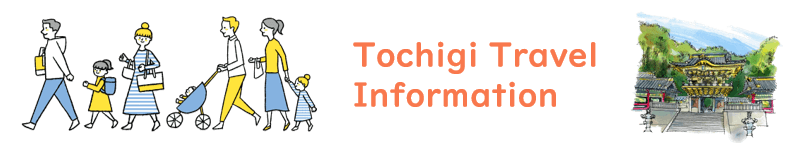栃木県下都賀郡野木町
『熊野神社』
野木町南西部の野渡地区の鎮守として崇敬されてきた神社で、御祭神として伊弉諾尊を祭り、創建は約1300年前と伝わる古社です。
近くには、国指定重要文化財の野木町煉瓦窯(ホフマン式輪窯)もあり、熊野神社のそばにも煉瓦でできた壁が見られます😊
こちらのブログでは、熊野神社の歴史や境内の様子についてご紹介させて頂きます。
[aside type=”boader”]【基本情報】
| 住所 | 栃木県下都賀郡野木町野渡 |
| 駐車場 | 有 |
| アクセス | マップを開く |
↓駐車場↓

栃木の人気宿検索
栃木県のどこに旅行したいですか?
熊野神社の歴史

野木町野渡地区にある熊野神社の歴史は古く、今から約1300年前の大宝3年(703年)に
紀州熊野からこの地へと訪れた川島対馬という方により創建されたそうです😊
なお紀州熊野とは、現在の和歌山県南部と三重県南部からなる地域のこと。
何らかの理由でほうぼうを旅していた川島対馬という方は、この野渡に住居を定め、開墾して村を起こしたといいます。
そして、次第に人口も増えていきますが、土地を鎮める神社がなかったことから
生まれ育った紀州の熊野神社の御分霊を、現在地に祭ったのが神社の始まりだそうです。
今では熊野神社の周りにいくつもの家がありましたが、こちらの村を起こしたのが川島対馬という方なら、周辺の地域に住む人々の中にはその子孫の方も多いのかもしれません😊
御朱印
調べてみたところ、熊野神社では現在御朱印の授与などは行われていないようです。
もし今後御朱印の授与などが始まりましたら、こちらでご紹介させていただきます。
ささら獅子舞
栃木県野木町野渡の熊野神社祭礼。明日、明後日とあるらしい。花傘の山車が出るほか、ささら獅子舞もある。平成16年4月10日に見に行ったが、ささら獅子舞はちゃんと見れなかった。一度じっくり見たい祭だ。 pic.twitter.com/3uTdSRVyXk
— Kame. Y (@kame_matsuri) April 6, 2018
熊野神社では、春の4月の例祭の際に、魔除けや豊作を祈りささら獅子舞が奉納されています。
今から約500年前の、古河公方足利成氏の時代から続くと伝わる野渡の伝統的な行事で
獅子の踊り手や、棒の演者・太刀使いも、全て子供が演じているのがこの舞の特徴です😊
ささら獅子舞では、木ぐるまを付けた山車が、色鮮やかに飾り立てた笠鉾を揺るがせながら先導する様子も見られるそうです。
提灯もみ
栃木県野木町 野木神社 提灯もみ
— 駅弁の人 (@ekibennohito) December 3, 2017
神楽もあり、時は進み、夜7時の提灯もみ開始を待ちます
そして…#野木町 #野木神社 pic.twitter.com/s3jH5WR2NT
熊野神社がある野木町には、フクロウが営巣することでも知られる野木神社もあり
こちらでは毎年12月3日になると、提灯もみという伝統的な行事が開催されます。
提灯もみでは、地元の子供や若者が、竹ざおの先につけた火のついた提灯を、掛け声を掛けあいながらぶつけあう様子が見られ、毎年多くの方が見に訪れる大きなお祭りです😊
なお提灯もみは、七郷まわりとも呼ばれており、これは、野木神社の神領である旧寒川郡の迫間田、寒川、中里、鏡、小袋・井岡、網戸、下河原田の計七郷を以前は巡り歩いていたためで
なんと建仁年間(1201~1204)から続いているそうですが、今ではその規模も小さくなり、野木神社周辺と、熊野神社がある野渡地区に限られて開催されているそうです。
↓秋の野木神社境内↓

また、以前の七郷巡りにおいては、出社の日を御出、帰社の日を御帰りと言いその祭りは御出社祭、御帰社祭と呼ばれるようになりました。
ちなみにこの御出社祭や御帰社祭は、鎌倉時代に源頼朝から神田と神馬が献上されたのをきっかけに始まったそうです😊
七郷巡りにおいては、美しく飾り立てた五頭の馬に、御神霊の宿る鉾を持った神官が分かれて乗り、多くのお供を連れて行列を組みながら、華やかに巡ったそうです。
また、各郷から選ばれた裸の若者が精進潔斎(神事や参拝前に、酒や肉を断ち、心身を清めること)し、高張り提灯をかざして行列に加わり
村境にさしかかると、御神霊を少しでも早く自分の村に招こうとする若者の間で激しくもみあったことから、別名裸もみとも呼ばれ、これが提灯もみのルーツとなったそうです😊
それが、次第に長い竹に提灯をつけぶつけあうようになり、また七郷巡りを終えて神社へ戻る、御帰りの際に行われるようになりました。
まとめると、現在は七郷巡り自体は行われていませんが、お祭りの中で生まれた提灯もみが、12月3日の御帰社祭の日に行われる伝統的な行事として受け継がれています。
古河の提灯もみとの関係
#いばキラフォト
— けぇぷぅ。art_relax (@keikosnow) January 24, 2018
地元の茨城県古河市の
『 提灯もみ祭り 』
毎年12月にやる関東の奇祭と呼ばれるお祭り。
20mの長い竹竿をぶつけ合い、提灯を消したほうが勝ち💡
バチンバチン❗とぶつかる音は迫力があり、竹竿を支えてる人々が力を合わせている様、飛び交う掛け声、ザ・お祭りという感じです🙌🎵 pic.twitter.com/CVS3pASzUz
なお、提灯もみといえば、お隣の茨城県古河市で開催される古河提灯竿もみまつりも有名で、こちらも江戸時代から続く伝統的な行事です。
そして実はこの古河提灯竿もみまつりは、野木神社の提灯もみに由来しているそうで
以前は古河藩に属していた野木町が、明治期の廃藩置県により栃木県の一部となったのがきっかけとなり始まったのだそうです。
それまで古河の人も野木町まで行ってお祭りに参加していたものの、地域が別れてしまったため
古河の人たちが独自に始めたものが、今も古河提灯もみまつりとして受け継がれています😊
境内紹介
野木町野渡地区の鎮守・熊野神社の境内の様子についてご紹介させて頂きます。
大きなイチョウの木が目印の熊野神社は、境内の入り口から社殿までまっすぐに参道が続いており、その間には計三つの鳥居があります。
↓一の鳥居(1890年建立)と↓
大きなイチョウの木

一つ目の鳥居は、1890年の建立で、明治期に建てたられた貴重なものです。
次に現れる二の鳥居は、実はこちらが最も古いもので、1833年に建てられたものになります😊
↓二の鳥居(1833年建立)↓

西暦1833年と言えば、江戸時代後期の天保年間であり、ちょうどこの頃から、東北地方を中心に天候不順が何年も続いて、天保の大飢饉へと発展していく頃のものです。
天保の大飢饉では多くの人々が食糧不足に苦しみますが、中にはそれを救おうと尽力された人々もいて、市貝町の入野家の方もその一人。
国指定重要文化財の入野家住宅は、天保の大飢饉に苦しむ人々を救うための救済事業として建てられたもので、立派なお屋敷でしたので、気になる方には是非見てみてほしいです😊
そして三つ目の鳥居は比較的新しく、2008年の建立だそうで、まだ綺麗でした。
↓三の鳥居(2008年建立)↓

この三つ目の鳥居をくぐった先で出迎えてくれるのが、神社を守る計六体の狛犬です。

まず一番手前の二体の狛犬は、逆立ちをしている大きな狛犬で、1949年の建立です。
↓一番目の狛犬(1949年建立)↓


この狛犬の台座には奉納関係者の名前があり、その中に川島という名前があったのですが
川島といえば、こちら野渡の熊野神社を創建された川島対馬という方と同じですので、もしかしたら子孫でしょうか😊
約1300年前の創建と伝わる神社ですので、もし子孫の方だとしたら凄いことですね。
そして二番目の狛犬は、1920年の建立で、子取り・玉取りの狛犬です。
↓二番目の狛犬(1920年建立)↓


この子取りの狛犬が連れている子獅子の表情がなんとも愛らしく、癒されました😊

そして拝殿の手前にもう二体狛犬がおり、そちらは1928年の建立です。
↓三番目の狛犬(1928年建立)↓


こちらの三番目の狛犬は、左右の阿形像・吽形像ともに子獅子を連れており、吽形像の子獅子の表情も印象的でした。

三つの鳥居に、三列六体の狛犬、またその途中には境内社もいくつかあり、木々も生い茂り、とても厳かな雰囲気に包まれている神社です。

なお、本殿を囲う透塀から中をのぞいてみると、そちらにも二体の狛犬がおり、合計すると熊野神社の狛犬は計八体にもなります。
そして、その本殿前の二体が、おそらく熊野神社で最も古い狛犬のようです😊
熊野神社の拝殿もまた立派で、木鼻には、霊獣である獅子と獏の彫刻が施されていました。


木鼻の装飾には、獏によく似た像の装飾が施されている場合もあり、鼻が長い所や、牙がある所もよく似ているのですが
獏の場合は目がギョロっとしていて、全身を巻き毛で覆っていたり、獅子のように爪がある所などから、見分けることが出来ると言います😊
おそらく普段はほとんどひとけのない神社ですが、参道からここまで綺麗で、地域から大切にされている神社であることが分かります。
境内には、1856年に栃木県今市で70年の生涯に幕を閉じられた、二宮尊徳像もありました。
↓二宮尊徳像(1932年建立)↓

二宮尊徳(二宮金次郎)翁は、栃木県日光市の報徳二宮神社境内の墓所にて眠られています。
熊野神社とレンガ道
熊野神社の境内沿いの道を歩いてみると、境内の壁が、積み上げた煉瓦で埋め尽くされている様子を見ることが出来ました。

これはなにかというと
実は野木町には、かつて東京駅の駅舎の煉瓦も焼成していたという、野木町煉瓦窯(旧下野煉化製造会社煉瓦窯)があり
かつてこの道は、そのレンガを馬車で古河駅まで運ぶ道として使用されていたそうで、通称レンガ道と呼ばれています。
そしてこちらの熊野神社沿いの煉瓦の壁は、大正15年に、熊野神社境内の土止土盛工事に使用された時の名残だそうで
今は使用されていない野木町煉瓦窯も、この頃は現役で煉瓦を焼成していました😊
↓野木町煉瓦窯↓

野木町煉瓦窯は現在国の重要文化財に指定されており、中もとても立派ですので、野木町へ来た際には是非ご覧になってみてください。
最後に

こちらのブログでは、野木町野渡の鎮守・熊野神社についてご紹介させて頂きました。
熊野神社は、現在の和歌山県の方にゆかりのある方が建てた神社ということですが
今から1300年も前に、どういう経緯でこの場所に移り住んだのかが気になります。
また、野木町と言えばやはり煉瓦窯が有名ですが、その煉瓦を焼成していた頃の名残が残っているのも大きな見所だと思います😊
野木町煉瓦窯からも歩いて来られる距離にありますので、野木町煉瓦窯へお越しの際には、是非熊野神社もご覧になってみてください。
最後まで読んで頂きありがとうございました。